昔、日本史で学んだ鎖国。
外国からキリスト教が入り込み、広がるのを恐れた幕府が鎖国したというのは、だれしも知る理由です。
先日、とあるアメリカ人が「鎖国が日本にユニークな文化を発展させた」と言っていました。
最初あまりピンと来なかったのですが、その後、面白い記事*1を見つけたので、学んでみましょう♪

キリスト教への恐れ
江戸時代の初期、幕府は南部で徐々に影響力を増しているキリスト教の存在に危機感を抱いていました。
徳川氏中心の日本の制度は『身分』をしっかりと分けていました。
そのため、キリスト教が広がるとこの身分での統治制度が揺らいでしまいます。

そこで、政府は”島国”のメリットである、国境封鎖を行うことにしました、これが鎖国です。
この鎖国制度は200年以上続きました。
現代では、北朝鮮みたいなもんですね。
こう言うと、ネガティブなイメージしかありませんが、この200年以上の鎖国の間に、日本独自の文化・習慣などが根付いたというところも特筆すべき点です。
もったいない
鎖国して、外国との交易を持たないとしたことで、島国日本には何が起こったのか。
まず誰もが思いつくのは、食料・材料などが輸入できないので、全て国内であるもので賄う必要があります。
自給自足ったって当時は今みたいな農業技術や有能な肥料もなく、天候が悪い年は飢饉が起こっていました。
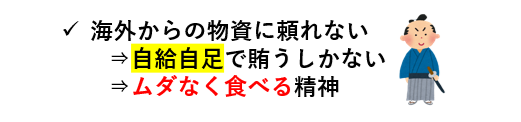
野菜だって葉っぱもお漬物にしたりしてムダにしませんし、世界ではあまり食べられないゴボウも食用としているのは日本くらいです。
この頃は仏教の影響で四足動物は食べていませんでしたが、後の日本で肉を食べるようになっても、例えば、焼き鳥では捨てることなく様々な部位を食べますし、魚でもエンガワなんて、ヒラメのヒレの部分ですが、そこも食べますね~
もったいない精神。
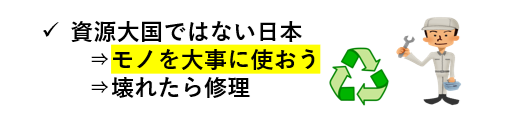
資源国でない日本ではものづくりにも影響があります。限りある資源の中で、長期使用、再使用などが当たり前となっていきました。
『長く使えるような品質の高いものを作ろう』という日本製品の強みの礎になっているのです。
資源の少ない国・日本が当時、化石燃料や化学肥料に頼らず3000万人の国民が自給自足できていたというのは驚くべき事実です。
スローライフ
鎖国下の日本は、とにかくスローライフでした。
それもそのはず、海外から新たな刺激が入ってくるでもなく、国内ではすでにあるものを再利用・長期使用する社会です。
漫然としたスローライフなはずです。

”もったいない“精神は、ろうそくの火も例外でなく、なるべく使用しないでいいように、人々の活動は日出から日没までに限られていました。
服だって穴があいたり、破れては修繕して着ました。ファッションや流行なんて関係ありません。スローライフ。
人糞だって無駄にしません。各家庭を回って、集めて肥料として農家に売る下肥問屋という業種さえありました。

これは今で言う『循環型経済』を体現しものです。
汚い話で恐縮ですが、この下肥は戦後まで、つまり昭和の時代まで普通にありふれたものでした。
ご察しの通り、このようなものを使うと、寄生虫の問題が出てきます。
こうして作られた野菜を食べると、寄生虫がおなかの中に住み着きやすいのです。
戦後の日本でもこれは大きな問題で、学校でギョウ虫検査がありましたね。僕のときもありましたが、今は化学肥料なので、心配もなく、2016年以降なくなりました。

そんなスローライフの中で、全国各地を旅しては、その情景や季節を短い詩に込める文化ができました。
平安時代からある和歌にエッセンスを与えたのは松尾芭蕉です、これが俳句の文化の夜明けでした。
時間の概念
スローライフ江戸で、もう一つ特筆すべきは時間の概念です。
当時の日本では、時間は季節に応じて違っていました。
大昔は十二時辰といって、干支と同じ12の動物で時間を表していました。各時間は、約2時間ずつです。
しかし、この十二時辰は、日の出と日の入の時間が関係するため、季節により各動物の時間が変わるのです。

江戸時代にもこの十二時辰に似た時間制度がありました。これは日の出と日の入の間(人々の活動時)を6つの時間帯に分けてあります。
なので日の長い夏場は“時間”が長く、冬は短くなります。
当時の日本には、分や秒といった不変の時はまだありません。
時間を知る術は、城や寺の鐘の音でした。
このように自然界をありのまま受け入れ、それに合わせた生活を送る鎖国下の日本人は、季節や自然への感受性が高く、環境に優しい生活習慣を身につけて行ったと考えられます。
自然と生きる
江戸時台中期以降、地方産業で、綿糸や製油、製糸、製紙、酒造などが栄え始めました。
それとともに、季節ごとに繁栄を願う"祭り"が行われるようになります。
桜の見れる春には豊作を願い、秋には収穫を祝いました。
このような全国各地で見られる祭りというのも、鎖国による間接的な影響でできたわけです。

もちろん、根底には日本人の持つ「自然との調和」「自然に宿る神」という観念もあるでしょう。
日本人と自然をつなぐ文化には例えば、坐禅があります。
坐禅そのものは仏教の影響が大きいですが、目的は静寂で平穏の空間を作り、”自然”と一体化することです。
戦後の日本は高度経済成長期を迎え、いまや先進国の1つとなり、我々は便利で豊かな生活を享受しています。一方で、地球温暖化などの環境面への懸念が日々増大し、SDGsなどといって”持続可能な”地球に優しい生活を目指そうとしています。
これはまさに鎖国下の日本人がしていた生活への回帰(もちろん科学技術の発展があるので上位互換)であるとも見れます。
では、また(^^♪